
2018年冬季オリンピックが約二週間後に迫る中、カヌー薬物混入事件が今世間を騒がせている。その関連事件として、1994年に起こった、 “ケリガン襲撃事件” (全米選手権前のフィギュアスケーター、ナンシーケリガンが暴漢に襲われたことで出場不能に追い込まれた事件。ケリガンのライバル選手、トーニャ・ハーディングの元夫などが逮捕された。)が、再度メディアで度々登場している。
「何から何までとても型破りだったわ。従来のような骨組みが全く取られてなかったの。レーンを選ばなくてはいけないのか、レーンを組み合わせる必要があるのか、全然わからなかった。モキュメンタリーのような感じでもあるし、ダーク・コメディでもあるし、実際に起こった人物が、実際に辿った人生についてのことでもある。しかも、皆、起こった事件やそれに関連する人々に対して、既に強い思いを抱いてしまっている。それをそのまま引き継ぐべきなのか、そして引き継ぐとしたらその思いはどういうものなのか…ひとつひとつのシーンに対して、たくさんのことを考えたし、話し合いながらつくったわ。
今27歳になったばかりのわたしが、トーニャの14歳から45歳を全て演じるということも、挑戦のうちの一つだった。でも、伝記映画の中で、1人の俳優が作品を通して同じ1人の人物を演じることは、 “観客の登場人物への感情移入”ためにとても重要だと考えているから、どうしても譲れないものだった。あともうひとつ、この映画をつくるにあたって直面したことは、期間がとても短く、予算も少ないにも関わらず、オリンピックという華やかでお金のかかるシーンがたくさんあるということ。そんな型破りな企画で、資本家は誰もたくさんのお金をだそうとするはずがなかった。」
「I, Tonya」は、1100万円の低予算かつ31日というアメリカ映画においてはかなりのタイトスケジュールの中で、制作された。マーゴットは、一日に8つや9つのシーンを撮ったこともあったそうだ。そんな中で、彼女はもちろん、ヘア・メイクアップチームにとっても、様々な挑戦が重なった。
ヘア・メイクアップチームは、昨年、「Ghosts of Mississippi」でアカデミー賞にノミネートされた、デボラ・デノバーを中心にまとめられた。
また、劇中に出てくる数々のかつらを担当したのは、アドルサ・リー。彼女は、2014年、これまた低予算でつくられた、「ダラス・バイヤーズクラブ」で、メイク・ヘアスタイリング賞のオスカーを受賞したことで知られている。チームは、実力のある豪華なメンバーによって構成された。
多い日は一日に7.8回のチェンジがあり、大忙しな日々が続く中、デボラまとめるチームは、 “真実の物語を伝えている”ということを観客に感じてもらうために、トーニャの試合やインタビューを何度も繰り返し観て、細部まで研究したという。特に、氷上での競技のシーンを撮影する時は、口紅やアイシャドウの色から、ネイルの色まで、実際のものに極限まで忠実になることにこだわったと、デボラは話している。確かに、予告編を観ていても、写真を見ていても、マーゴットとトーニャを時に見間違そうなほど、実によく再現されているのがわかる。
このように、「真実の物語」を伝えるということに、たくさんの人が力を尽くす中で、主役であるマーゴットは、「今実在する人物を、映画の中で表現すること」について、どう考えていたのか。
マーゴットは、この映画が特に、暴力シーンを扱う作品であるため、それらを “正しく扱って表現”することを常に心に留めていたという。その、”正しく扱う” とはどのようなことなのかについて、マーゴはこう話している。
「問題をシュガーコーティングすること(曖昧かつ遠回しに、真意の角を取って表現すること。)は正しく扱ってないということになる可能性があるわ。それをエンターテイメントの一部として使うとしたって、誤解を生んだり、正確に表現できていないことになってしまえないから、とても慎重になる必要があった。でも、曖昧にするのではなく、逆に少し強調することで、生まれる利点がある。それは、キャラクターの中のたくさんの欠点や短所を、観客たちが時々自分自身の中に見い出せるようになることがある、ということよ。その微妙で繊細な表現を正しく描くことができる監督を見つけられないなら、この映画を最初からつくるべきではないと、わたしは言っていたくらいだった。」
そして、マーゴットがいう、”微妙で繊細な表現”を見事に成し遂げることができる人物が、監督についた。「ラースとその彼女」を監督したことで知られる、クレイグ・ギレスピーだ。彼でなくてはどうしてもこの映画が成り立たなかった理由を、マーゴットはこう挙げている。
「クレイグが監督となった決め手は、彼がキャラクターについて、批判を一つも話さなかったこと。人が、キャラクターを馬鹿にしていたり、蔑視している時って、すぐにわかるもの。クレイグだけは、キャラクターを理解し、共感できる部分を見つけたいと心から思っていた。彼は私たちに、たくさんの技術的な解決方法を示してくれたの。正解が掴みにくくて、現場の全ての人が自分の意見を言っているうちに、答えが出ずにこんがらがってしまっているような状況の下で、彼は、実際にそれを解く方法を常に分かっていた。」
「たとえば、 “ここではワイド・ショットで撮ろう”、 “ここでは、観客に感情を強要させないために、音楽を入れない方がいいと思う”、”あのセリフが入るまで、観客に不快な気持ちでいてもらうために、そのビートを鳴らし続けよう” というようにね。彼は、私たちが解くのに困っている “なぞなぞ”に対して、とても明白な糸口を教えてくれた。」
また、監督が商業映画の世界で働いていたことが低予算・短期間の撮影中とても役に立ったと、マーゴットは考えている。彼の頭の中で、どの瞬間に時間とお金を使うべきか、撮る前に全てみっちりと計算されていたからだ。「こんなにタイトなスケジュールの中でも、急かされているようには一度も感じなかった」とマーゴットは話している。
1994年の事件当時、 トーニャ・ハーディングに対して、 “最低なことをした乱暴者”というイメージが、人々の間に強く根付いていた。しかし、この映画を観たたくさんの人が、「トーニャに共感した」という感想を寄せている。傍若無人なトーニャの態度を、妥協して緩和させることなく演じ、かつ観客を彼女への共感の気持ちへと導く為に、マーゴットが心がけていたことは何だったのか。
「わたしは彼女を “みんなの批判の犠牲者”とも、“悪役” とも表現したくはなかった。ただの1人の人間として、表したかった。やっぱり最終的には、良くも悪くも、どんな人でも、私たちは “ただの人間”である、ということを伝えたかったの。私たちは、6秒の録音音声と、新聞の巨大な見出しだけを見て、 “トーニャは、キリガン選手の人生を台無しにした”、と彼女を批判していたけれど、そうすることで今度は私たちが、トーニャの人生を壊しているということを、よく考えていなかった。」
そして、彼女を“ただのみんなの批判の犠牲者”としないためにも、彼女の反抗的かつ挑戦的な部分は、しっかりと描きたかった、とマーゴットはいう。
「監督が、 “ジェフ(トーニャの元夫)がトーニャに暴力を振るうシーンで、トーニャはジェフを叩き返さなくてはいけない”と言ったの。彼女は、確かに反抗的で挑戦的であった。そのことを、ちゃんと観客に観てとって欲しかったから。」
“ウォルフ・オブ・ウォール・ストリート” でのナオミ・ラパグリアや、”スーサイド・スクワッド”でのハーレー・クイーンなど、一見演じる上での感情移入が難しそうな役を、演じこなすマーゴット・ロビー。「人間というのは誰しも汚い部分を持っているわ。わたしはそうじゃない人物を演じたくない。少しとっ散らかっているキャラクターの方が演じていて楽しいもの。」と話すマーゴットだが、今回は、トーニャと自身のどういう部分を関連づけたのか。「ナオミを演じた時に比べれば、トーニャというキャラクターには、理解できる部分がたくさんあった。」と、マーゴットは話す。
「トーニャを演じるにあたって、彼女がアスリートであること、そして最終的には負け犬であるという事実に焦点を置いたわ。わたしは、ギャングの映画を観ていて、負け犬が最終的に勝ち上がる話が大好きなの。彼女の野望についてはよく理解することができた。あと、ジェフとの関係性についても、いくつかの側面においては共感できるところがあった。ジェフは、ただの悪役じゃないのよ。トーニャとジェフは実際に愛し合って楽しい時を過ごした時期もあった。ジェフが暴力を繰り返し振るシーンで、観客はきっと、”なんで彼女は彼を捨てないの⁉︎”と思うはず。でも、彼しか、人間として価値がある、という確証をトーニャに与えることができなかったの。それは、スケートの審査員が決してトーニャに与えなかったものなの。」
マーゴットは、トーニャを演じる際、 “座っている時は常に前かがみに乗り出す”ことを心がけたという。それは彼女が常に、母やジェフやメディアや世界から、”自分には価値がある、という確証” を欲しがっている人物であるということを表すためだ。
マーゴットは、トロント国際映画祭で、観客達の反応を待っている時、まるでトーニャが審査員達が出すスコアを待っているような気分だったという。ウォルフ・オブ・ウォールストリートよりも、スーサイド・スクワッドよりも、今までマーゴットが出演した映画が観られる瞬間として、一番緊張した、と話している。結果は、観客賞次点一位。トーニャ・ハーディング自身がこの作品を初めて鑑賞したのも、この映画祭でのことだった。その時のことについて、そして鑑賞後のトーニャの反応について、マーゴットはこう語る。
「彼女の人生の最高の瞬間と最低の瞬間の両方が、たった2時間の映画の中で描かれていることについて、トーニャ自身がどんな反応をするのか怖かったわ。でも彼女はとても気に入ったと言ってくれた。それと、映画の中での彼女の母との関係性の描き方は、とても当を得ているとも話してくれた。でも、作中には何ヶ所か事実と違う部分があるとも言っていた。キリガン選手への脅迫の手紙の存在を、トーニャは知っている、という描き方を映画中ではしたのだけれど、実際はトーニャは本当にその手紙の存在を知らなかった。でも、ジェフの視点からみると、トーニャがまるでその手紙の存在を知っているように思えた。だから、わたしはそのように演じなくてはいけなかったの。映画の中では、トーニャの視点からの出来事だけではなくて、他の登場人物の視点から見たトーニャ自身、そして出来事が描かれていることもある。制作側は、当初からトーニャに、彼女の人生のドキュメンタリーを作っているわけではない、ということを伝えていたから、トーニャからその部分を変更するようには別に頼まれなかった。」
トーニャ・ハーディング自身は、「この映画の中で大きく二つ実際とは異なる部分がある」ということを、あるインタビューで話している。
一つ目は、映画中でトーニャが吐く汚い言葉の数々についてだ。
「映画では、10秒ごとに汚い言葉を吐く人のように描かれているけれど、普段は怪我した時か、とても悪いことが起こったときぐらいしか言わないのよ。」とトーニャは言う。
二つ目は、トーニャが自らウサギを狩って、コートをつくる、というシーンについて。実際は、そのコートは買ったという。彼女自身は熱烈な毛皮愛好者だが、動物愛好者からの批判を恐れるあまりに外へ来ていくことは出来るだけ避けているそう。
発せられる汚い言葉の数々や、ウサギを狩ってコートをつくるという行為は、確かに、トーニャの、 “反抗的かつ挑戦的”というイメージを強調するような表現である。2時間しかない映画の中では、一つ一つの細かい描写が、観客の人物に対するイメージを左右する。また、特に今実在する人物の伝記映画となると、そこで得た印象をその本人に当てつける人も多くいるだろう。しかしこれは、マーゴットと監督が「強調されるべき」と思った、トーニャの性格の側面であり、決してただ単に、映画としてのエンターテイメント性だけを思って付け加えられたのではない。
真実の物語を伝える、ということを前提に、事件を曖昧にすることなく表現しつつ、ドキュメンタリーではないからこそ出来る表現(一つの出来事を数人の登場人物の視点から描くこと、キャラクターの性格を強調すること、など)の両方を見事に行ったとして、批評家からも数多くの絶賛を受けている「I,Tonya」。日本での公開は今年の初夏を予定されている。
参照記事
https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/12/margot-robbie-tonya-harding-transformation-in-i-tonya/amp
http://deadline.com/2017/11/i-tonya-margot-robbie-movie-interview-1202216000/amp/
http://www.news.com.au/entertainment/movies/tonya-harding-reveals-her-two-big-problems-with-i-tonya/news-story/d40f8ddb75011dfcee970659074a7a38
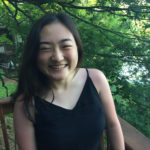
樋口典華
映画と旅と本と音楽と絵画が、とにかく好きで好きでたまらない、現在、早稲田実業学校高等部3年生。興味をもったことは、片っ端から試していく性格です。

コメントを残す