
 今年のカンヌ国際映画祭は、第70回記念として2017年5月17日から28日までの日程で開催予定である。しかし、今年は開催前から様々な政治的論議に事欠かない。まず、イタリアの伝説的映画女優クラウディア・カルディナーレをフィーチャーした公式ポスターが、彼女のスタイルを(現代的で痩せて見えるように)意図的にレタッチしたとして、フランスのメディアやSNSを中心に大きな論争を巻き起こしたのだ。批判者の論点は、それが女性の身体に対する幻想を煽るものであること、そして完璧なスタイルであるとも賞賛された映画史上のミューズに対するリスペクトを欠いた振る舞いであるということの二点であった(#1)。しかし、カルディナーレ本人がフランス版ハフィントン・ポストのインタビューに答える形で、レタッチは単にライティングを強調し夢のようなキャラクターを造形したものであり、この論争は映画の間違った政治化であると反論することで、ひとまず沈静化した(#2)。
今年のカンヌ国際映画祭は、第70回記念として2017年5月17日から28日までの日程で開催予定である。しかし、今年は開催前から様々な政治的論議に事欠かない。まず、イタリアの伝説的映画女優クラウディア・カルディナーレをフィーチャーした公式ポスターが、彼女のスタイルを(現代的で痩せて見えるように)意図的にレタッチしたとして、フランスのメディアやSNSを中心に大きな論争を巻き起こしたのだ。批判者の論点は、それが女性の身体に対する幻想を煽るものであること、そして完璧なスタイルであるとも賞賛された映画史上のミューズに対するリスペクトを欠いた振る舞いであるということの二点であった(#1)。しかし、カルディナーレ本人がフランス版ハフィントン・ポストのインタビューに答える形で、レタッチは単にライティングを強調し夢のようなキャラクターを造形したものであり、この論争は映画の間違った政治化であると反論することで、ひとまず沈静化した(#2)。
次に問題となったのは、Netflix製作による『オクジャ』(ポン・ジュノ)と『The Meyerowitz Stories』(ノア・バームバック)の2本の作品がコンペティション部門に選出されたことである(#3)。Netflixのビジネスモデルは、製作した作品を動画配信サービス(SVOD)で全世界配信することを優先しており、劇場公開を重視していない。今回の2作品もフランスで劇場公開が予定されていないことから、これが映画館と共に歩んできたフランスにおける映画のアイデンティティを大きく揺るがすものであるとして、激しい議論を巻き起こしたのだ。映画祭は公式コメントとして、次のように述べている。
「我々はこれらの作品がフランスで劇場公開されないことで大きな懸念を呼んでいることを知っています。映画祭はNetflixに動画配信だけではなく、フランスでの劇場公開も行うよう要請してきましたが、最終的に合意は得られず無駄に終わりました。」
 実は、フランスの映画館で公開されない作品がカンヌに正式出品されるのは、今回が初めてではない。ワイルド・バンチが2014年に製作した『ハニートラップ 大統領になり損ねた男』(アベル・フェラーラ)は、フランスでの劇場公開を経ないままカンヌでコンペ外上映され、同時にワイルド・バンチのVODサービス「FilmoTV」で配信された。また、NetflixのライバルであるAmazon Studio製作による映画作品も、これまでカンヌで上映された際に大きな問題を起こしてはいない。昨年はAmazon Studio製作による5本の映画がカンヌのラインナップに加わり、しかもそのうち『カフェ・ソサエティ』(ウディ・アレン)は、映画祭のオープニング作品とまでなった。では何故、今回Netflix作品がこれほど大きな問題となったのか。それは、Amazon Studioのビジネスモデルが全世界的な劇場公開を許容するものであり、そしてフェラーラ作品がコンペ外上映であったのに対して、今回の2作品がコンペティション部門に出品され、かつNetflixのビジネスモデルがフランスの映画館にとって直接的な脅威となるからだ。今回の決定に強く抗議してきたFNCF(フランス映画館連盟)のマルク=オリヴィエ・セバーグは、次のように述べている。
実は、フランスの映画館で公開されない作品がカンヌに正式出品されるのは、今回が初めてではない。ワイルド・バンチが2014年に製作した『ハニートラップ 大統領になり損ねた男』(アベル・フェラーラ)は、フランスでの劇場公開を経ないままカンヌでコンペ外上映され、同時にワイルド・バンチのVODサービス「FilmoTV」で配信された。また、NetflixのライバルであるAmazon Studio製作による映画作品も、これまでカンヌで上映された際に大きな問題を起こしてはいない。昨年はAmazon Studio製作による5本の映画がカンヌのラインナップに加わり、しかもそのうち『カフェ・ソサエティ』(ウディ・アレン)は、映画祭のオープニング作品とまでなった。では何故、今回Netflix作品がこれほど大きな問題となったのか。それは、Amazon Studioのビジネスモデルが全世界的な劇場公開を許容するものであり、そしてフェラーラ作品がコンペ外上映であったのに対して、今回の2作品がコンペティション部門に出品され、かつNetflixのビジネスモデルがフランスの映画館にとって直接的な脅威となるからだ。今回の決定に強く抗議してきたFNCF(フランス映画館連盟)のマルク=オリヴィエ・セバーグは、次のように述べている。
「私たちはNetflix作品が(たとえ映画祭による公式上映であったとしても)コンペ外で出品されることに何の問題も感じません。しかし、コンペティションはショーケースなのです。もしカンヌで賞を取った作品が劇場公開されないとしたら、その映画祭にどんな意味があるのでしょうか?」
問題は、従って2点ある。一つは、カンヌ映画祭のコンペティション部門が映画界に果たすべき象徴的役割と意義。これは映画と映画館の存在を巡るフィロソフィーの問題である。そしてもう一つは、Netflixのビジネスモデルと鋭く対立するフランス独特のメディア法の存在だ。実は、フランスには映画館を守るため、劇場公開後36ヶ月は動画配信サービスで映画を流すことが出来ないように定めた法律がある。このため、Netflixがもし今回の2作品をフランスで劇場公開すれば、その後3年間は動画配信できなくなってしまうのだ。これは彼らのビジネスと根本的に矛盾してしまう。この矛盾を解決するため、Netflixはフランスのメディア法に抵触しない(VOD配信を阻害しない)小規模なプライベート上映の形を模索しているが、カンヌ出品作品としてより大規模な公開を求めるフランス映画庁によって現在のところその可能性を否定されている(#4)。
 論争の過熱を受け、カンヌ国際映画祭は5月11日に新たな声明を発表した。それは、『オクジャ』と『The Meyerowitz Stories』の2作品は今年のコンペ作として残されるが、2018年から適用される新たなルールとして、「カンヌ国際映画祭のコンペ部門を争う作品は、フランスの映画館で配給されなければならない」とするものだ(#5)。これに対し、ヴェネチアとトロントからすぐさま連帯の声が上がった。ヴェネチア国際映画祭でディレクターを務めるアルバート・バルベーラは、微妙なニュアンス(ヴェネチアもトロントもNetflix作品を過去に公式上映している)を含めながら次のように述べている(#6)。
論争の過熱を受け、カンヌ国際映画祭は5月11日に新たな声明を発表した。それは、『オクジャ』と『The Meyerowitz Stories』の2作品は今年のコンペ作として残されるが、2018年から適用される新たなルールとして、「カンヌ国際映画祭のコンペ部門を争う作品は、フランスの映画館で配給されなければならない」とするものだ(#5)。これに対し、ヴェネチアとトロントからすぐさま連帯の声が上がった。ヴェネチア国際映画祭でディレクターを務めるアルバート・バルベーラは、微妙なニュアンス(ヴェネチアもトロントもNetflix作品を過去に公式上映している)を含めながら次のように述べている(#6)。
「何よりもまず、私は(カンヌ映画祭代表を務める)ティエリー・フレモーへの連帯を表明したい。これは決して簡単な決定ではなかったはずだ。ここには、明確なルールなしに急激な変容を強いられているマーケットの最後の激痛がある。劇場主から配給会社、プロデューサー、そして映画作家に至るまで、実に多くの関心と目的がここでは関係している。しかし、映画祭の役割はそのいずれからも独立しているべきだ。それは、質の高い映画を広め、選び出し、光を当て、どこで上映されたかを問わずそれらをサポートするべきものであるのだ。」
一方、Netflix社CEOのリード・ヘイスティングスは、カンヌの決定に対して自身のFacebookで「業界のエスタブリッシュメントが我々を閉め出した」と述べた(#7)。フランスの映画会社ワイルド・バンチもまたNetflixの姿勢に賛同している。過激な発言で知られる同社共同創立者のヴィンセント・マラヴァルは次のように述べている(#8)。
「(カンヌの新しいルールは)馬鹿げている。それはフランス植民地主義の反映であり、彼らは自分たちのルールを他者に押しつけようとしているんだ。イタリアで公開されていないフランス映画がヴェネチア映画祭から閉め出されるだろうか?ポン・ジュノの映画は韓国で製作され、韓国では拡大公開されているんだ。話にならないよ。」
映画祭が果たすべき象徴的役割はともかく、今回のNetflix作品に関する論争において具体的問題となっているのは、同社のビジネスモデルと劇場公開から36ヶ月のVOD放映を禁じるフランスのメディア法との対立である。そして、この法律を現在変えようとしているのが新たに大統領に選出されたエマニュエル・マクロンであるのだ(#9)。フランスのメディア法は、他にも劇場公開映画を宣伝するテレビコマーシャルを禁じるなど、ハリウッドの商慣習とは大きく異なる条項を数多く備えている。伝統的文化産業のパワフルなロビー活動から比較的自由な立場にあると言われるマクロンは、映画産業を保護するため制定されたこれらの法律に大きな改革を持ち込もうと目論んでいる。フランスのメディア法とNetflixのビジネスモデルとの間に顕著な矛盾がなくなれば、今回の問題はテクニカルな意味では解決される筈だ。(例えば日本からカンヌのコンペに出品しようとする場合、事前にフランス配給を決めなければいけないという問題は残るが。)
しかし、それでもまだ問題はある。果たしてマクロンがメディア法を変えたとして、それがフランス映画、あるいはフランス経済、そしてさらには映画そのものに対してポジティブな効果を及ぼすだろうかという問題だ。先日行われた大統領選挙において、フランス映画界はおしなべて最終的にマクロンを支持する姿勢を打ち出した。これは、マリーヌ・ル・ペンによる極右政権の誕生を恐れてのことだが、グローバリズムとローカルな価値観の対立においては、今回の問題に表出されるように決してマクロンを支持しているわけではない。しかし、ここでヘイスティングスの言うように、新たなメディア勢力の台頭によって変わりつつあるグローバルな世界と、それを受け入れられない旧弊なフランス既得権益の対立として問題をとらえるのは、やや単純すぎるように思われる。
大統領に選出されるまでいかなる公職選挙でも選ばれた経験を持たないマクロンは、いわゆる地盤を持たない政治家である。実際、最初の大統領選投票において、生まれ故郷のアミアンで彼は20ポイントの大差を付けられてフランソワ・フィヨンに敗れている(#10)。そのマクロンを強力に支持し、彼の新たな地盤となったのはブルターニュだ。実に4人のうち3人までがここではマクロンに投票したとのことである。かつてド・ゴールを強力にバックアップし、強固な保守的土壌で知られたこの地域は、現在ではきわめてリベラルで左翼的な政治的風土を誇っている。この「転向」の理由を鮮やかに分析し、それを「ゾンビ・カトリシズム」と名付けたのは、エマニュエル・トッドである(#11)。
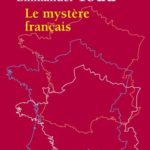 トッドがエルヴェ・ル・ブラーズとの共著で出版した「Le Mystere francais(フランスの謎)」によると(#12)、かつてカトリックが強固に根付いていたブルターニュは、その宗教的儀礼の拘束が衰退した(カトリックが宗教として死んだ)後にまで残された強力なコミュニティ意識や男女の役割に対する保守的観念によって、他の地域に比べ経済面、文化面、そして教育において大きな成功を収めたとのことだ。この成功体験がもたらしたオプティミズムによってブルターニュの人々は表層的にリベラルな政治的主張を持つようになったが、しかしその深層にあるのは、権威主義的で格差や不平等を容認する本質的に差別的な精神であるというのがトッドによる分析である。そして、マクロンの伝記作者マルク・アンドヴェルドは、世俗的家庭に生まれ12歳で洗礼を受けたものの、普段は教会に通わないマクロンの政治的主張こそ典型的な「ゾンビ・カトリシズム」のものであると述べた(#13)。
トッドがエルヴェ・ル・ブラーズとの共著で出版した「Le Mystere francais(フランスの謎)」によると(#12)、かつてカトリックが強固に根付いていたブルターニュは、その宗教的儀礼の拘束が衰退した(カトリックが宗教として死んだ)後にまで残された強力なコミュニティ意識や男女の役割に対する保守的観念によって、他の地域に比べ経済面、文化面、そして教育において大きな成功を収めたとのことだ。この成功体験がもたらしたオプティミズムによってブルターニュの人々は表層的にリベラルな政治的主張を持つようになったが、しかしその深層にあるのは、権威主義的で格差や不平等を容認する本質的に差別的な精神であるというのがトッドによる分析である。そして、マクロンの伝記作者マルク・アンドヴェルドは、世俗的家庭に生まれ12歳で洗礼を受けたものの、普段は教会に通わないマクロンの政治的主張こそ典型的な「ゾンビ・カトリシズム」のものであると述べた(#13)。
トッドとアンドヴェルドの主張をまとめると、つまり一見したところリベラルでグローバリズムに寛容なマクロンの政治的主張の根底には、自らの経済的優越に由来する「ゾンビ・カトリシズム」の楽天主義と権威主義、格差容認の姿勢が存在しており、それはポスト・コミュニズム(カトリシズムと同様に宗教として機能し人々をつなぐ役割を果たしたコミュニズムは、ヨーロッパでは80年代に死んだというのが彼の認識だ)の空白にあえぐフランスの他の地域にとって決して自らの問題を解決せず、むしろ極右勢力やポピュリズムへと誘惑される大きな政治的リスク、ないしは経済的破綻や格差社会を生み出すばかりだとのことである。
トッドはまた、日本はドイツと同様、「ゾンビ・カトリシズム」とは異なった形ではあるが、保守的な社会的風土がグローバル化された世界における経済的成功を生み出してきたとも分析している。(ただし、移民を受け入れることで若年労働力の補充を行ってきたドイツに対し、高齢化社会を放置してきた日本はそれ以上の成長を諦めたとのことだ。)この見方に従うならば、今回のカンヌの決定を日本から批判する立場もまた、自らの経済的下部構造に基づく偏ったものだとの誹りを免れることは出来ない。日本には日本の事情があるように、フランスにもフランスの事情がある。一概にそれを、新しい世界に適応できない既得権益の抵抗と片付けるのも、やはり抽象的な議論に過ぎないのではないだろうか。
#1
http://www.hollywoodreporter.com/news/cannes-poster-controversy-was-claudia-cardinale-retouched-989997
#2
http://www.huffingtonpost.fr/2017/03/29/claudia-cardinale-reagit-a-laffiche-du-festival-de-cannes-et-sa_a_22017817/
#3
#4
http://variety.com/2017/film/global/french-film-board-rejects-limited-release-for-netflixs-cannes-competition-films-1202424129/
#5
https://www.theguardian.com/film/2017/may/11/cannes-film-festival-takes-on-netflix-with-new-rule
#6
https://theplaylist.net/tiff-venice-festivals-react-cannesnetflix-battle-20170512/
#7
https://www.facebook.com/reed1960/posts/10154968673644584
#8
http://deadline.com/2017/04/netflix-cannes-film-festival-french-theatrical-exhibitors-dispute-okja-the-meyerowitz-stories-1202077688/
#9
http://deadline.com/2017/05/emmanuel-macron-wins-french-presidential-election-reactions-trump-hollywood-1202086351/
#10
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2017/05/the_region_that_explains_france_s_new_president.html
#11
http://www.catholicnewsagency.com/news/frances-new-president-is-a-zombie-catholic-41556/
#12
#13
http://www.regards.fr/web/article/marc-endeweld-macron-est-ideologiquement-le-bebe-de-hollande

大寺眞輔
映画批評家、早稲田大学講師、アンスティチュ・フランセ横浜シネクラブ講師、新文芸坐シネマテーク講師、IndieTokyo主催。主著は「現代映画講義」(青土社)「黒沢清の映画術」(新潮社)。
大寺眞輔(映画批評家、早稲田大学講師、その他)
Twitter:https://twitter.com/one_quus_one
Facebook:https://www.facebook.com/s.ohdera
blog:http://blog.ecri.biz/
新文芸坐シネマテーク
http://indietokyo.com/?page_id=14
コメントを残す