
DAUの現在
ロシア映画史上最大規模のプロジェクトDAUからのチャプターが今年2021年2月27日からシアター・イメージフォーラムおよびアップリンク吉祥寺、その他劇場にて公開される運びとなった。公開されるチャプターのタイトルは『DAU. ナターシャ』。ウクライナにソ連時代の科学研究所をつくり、現職の科学者や職員を配置、そこで生活させたという史上類を見ない規模の巨大な実験の一端が日本の映画ファンの目に触れる機会を得た。『DAU. ナターシャ』に銀熊賞をもたらした去年のベルリン国際映画祭での公開以降、本来DAUの各チャプターは世界各地の映画祭に出品されてゆく予定だった。しかし、新型コロナウイルスの世界的流行のため、その実現は果たされることが無かっただけに、日本での『DAU. ナターシャ』の公開は大きな驚きだ。
現在DAUは「隔離について、隔離された人々による、隔離状況下で撮影された、初の映画プロジェクト」と時宜に応じて自らを再定義するとともに、インタラクティブ・ストリーミング・プラットフォーム、DAU.comを開設。在宅での視聴に対応している。当サイトではコンサート映像や、科学とアートに関するドキュメンタリー・シリーズに加え、プロジェクトに関するその他のマテリアルを含む合計700時間分のフッテージの公開を予定している。(2021年1月現在、7つのチャプターがサイト上で公開されている。)『DAU. ナターシャ』の日本語公式サイトで「オーディション人数約40万人、衣装4万着、欧州最大1万2千平米のセット」と謳われているDAUの常識はずれなプロジェクトの全貌と、人々の怒りを招いた性的な拷問場面に代表されるプロジェクトの挑発的性質については、それぞれIndie Tokyoで過去に記事を掲載している。そこで今回は、欧米で批判を受けたイリヤ・フルジャノフスキー(Ilya Khrzhanovskiy)監督の人心操作、そしてDAUのキャストへの虐待疑惑を引き起こした『DAU. ナターシャ』におけるボトルを使った女性への拷問場面がどのように撮影されたのかについて、プロジェクト関係者たちの言葉を参照しつつ、新たにスポットを当ててみたい。拷問の撮影方法に倫理的な問題は無かったのか。映画でこの拷問を受けるナターシャを演じたナターリヤ・ベレジナヤ(Natalia Berezhnaya)は、去年の5月にようやくその重い口を開き取材に応じている。これにより前回の記事を書いた時点では見えていなかった諸事実が明るみに出ることとなった。なお、以下で語る事柄はDAUに関する前回の記事が前提になっているので、未読の方はこちらへ先に目を通されると理解が早く進むはずだ。[1]
乳児を巡る非難
DAUへと向けられた数々の非難のなかに、映画に登場した乳児についてのものがある。映画で乳児たちは個別に小さな檻に入れられ、実験へと取り出されていた。これについて、キャスティングプロセスとロンドンでのポストプロダクション、そしてドキュメンタリー映像の撮影に参加した元DAUスタッフのアルビナ・コワリョーワ(Albina Kovalyova)は、テレグラフ紙に掲載された自筆の記事で次のように述べている。「孤児院から連れてこられたダウン症の赤ちゃんに対する実験映像を見たとき、私はショックを受けました。」母親である自分の「直感が、何かがおかしいと告げていました。」また、幼児神経心理学の専門家であるオレーナ・サモイレンコ(Olena Samoilenko)も、乳児は撮影を拒んだり撮影中も中止を訴えることができないため、これは子供への暴力だとする意見をフェイスブックに投稿している。さらにこの件に関しては、DAUのセットのある地元ウクライナの検事たちも捜査に乗り出したという。一方でDAUの広報によると、これは「模擬実験」であるため、被害を受けた乳児はいないとしており、監督のフルジャノフスキーもセットには常に有資格の世話係が待機していたと語っている。コワリョーワによればフルジャノフスキーは彼女の感じたショックを「若い母親であるがゆえの心理作用」だと述べて彼女をなだめたというが、その際コワリョーワは自分が監督のうまいように「操られてしまった」(manipulated)と感じたという。[2][3][4]
「DAUの醜聞は監督が望んだことだった」
DAUのスタッフに対しフルジャノフスキーが行ったとされる「操作」または「コントロール」という言葉は、極端に言えばある種の洗脳行為のようなものとしてDAUを巡るスキャンダルでしばしば登場するキーワードである。DAUの演者たちが性的拷問に同意したり、性的な本番行為を行ったのも、監督による心理的操作やコントロールを受けたためだと、フルジャノフスキーは批判を受けてきた。彼がセットで女性を面接した際のセクハラまがいの質問や、ナイトクラブでのナンパ師ぶりなどを報じ、フルジャノフスキーに関する悪評の最も大きな源泉となっているGQ誌の記事を書いたジャーナリスト、ミハイル・イドフ(Michael Idov)もまたフルジャノフスキーによるコントロールを感じたと語っている。DAUの撮影中、このGQ用の記事の取材のためウクライナにあるセット(研究所)を訪問していたイドフは、カフェで給仕として働くオリガ(Olga Shkabarnya、『DAU. ナターシャ』にも登場している)と親しい仲になった。しかしイドフによれば彼と話しているあいだ「彼女は明らかにフルジャノフスキーの司令で演技をしていた」という。「僕が彼女に誘惑されてセットに留まるかどうかを確認するためにね。」(DAUのセットでは常に時代設定に合わせて研究所の職員を演じ、働くことがキャストの仕事だった。)ある朝イドフとカメラマンのセルゲイ(Sergey Maximishin)が入浴中のオリガを撮影していた際、オリガがタオルを使って髪を纏め上げているのを見たフルジャノフスキーはこれに激怒した。オリガのタオルの巻き方がフルジャノフスキーの決めた研究所での規定に反していたためだ。それがカメラマンのセルゲイの指示だとわかると、フルジャノフスキーは「私のスタッフは操り人形ではない」とイドフたちに言い放った。そして「もちろん操り人形さ。セルゲイのじゃなく、監督自身のね。」とイドフが思う間もなく、フルジャノフスキーは彼に囁いた。「我々のコラボレーションは終わりだ。ここから立ち去ってくれ。」
それはイドフにとって、GQから派遣されてきたセルゲイを送り返せという言外の意味を明らかに持っていた。セットでの滞在中、セルゲイは研究所の時代設定を真剣に受けとめず、ソ連当時使われていなかった言葉を口にしたり、人々の演技を常に冷やかし続けていた。セルゲイを送り返さない限り、イドフとフルジャノフスキーとの関係には亀裂が入るだろう。これを悟ったイドフは、自分のために同僚のセルゲイを裏切ることにしたという。皮肉にもこの行為は、ソ連社会で人々が政府への密告を強制されていたことをイドフに思い出させた。先のセリフを囁き終えたフルジャノフスキーを見ると、その口元には何故か笑みが浮かんでいたという。イドフは思った。自分に立ち退きを命じるこの通告も「ちょっとしたフルジャノフスキーの芝居なんだとね。なぜって、僕がこうしてフルジャノフスキーの意図に従い、飼い慣らされてしまった、というのは記事として面白いだろ?」だからGQの記事を通して「手伝ってやったんだ。フルジャノフスキーが専制君主のような天才として自画像を描くのをね。こうして彼は完全に僕をコントロールしたんだ。だが僕があの記事のことを誇るべきかどうか、いまひとつ自信が持てない。あれは僕が雑誌に書いてきた記事の中で一番出来の良いものだったが、僕があれを誇っているかというと、あまり自信が持てないんだ。」ここで覚えておきたいことは、イドフがあくまでフルジャノフスキーの「意を汲んで」彼を専制君主に仕立て上げる記事を書いたとしている点だ。イドフによれば、GQの記事の中でDAUのキャスト・スタッフを支配する暴君としてフルジャノフスキーの姿を悪し様に描写したのは、他ならぬ監督自身の意図するところであり、彼はこの監督に「操作されて」しまった操り人形の一人だった。[5][6]
DAUはどのように撮影されたのか
もしかするとこれはイドフが事態を面白おかしく拡大解釈しているだけかもしれない。しかし、イドフの記事は醜聞を拡散するだけでなく、DAUの名前を世界に周知する上で大きな役割を果たしたことは、フルジャノフスキーにとって歓迎される事実だろう。世界のメディアはイドフに続くかたちでDAUを人権侵害ぎみの問題ある映画プロジェクトとして取り上げてきた。これらの報道には、あたかもフルジャノフスキーがDAUの参加者たちのプライベートな性的営みや、「現実に起きた」拷問を不当に撮影してきたかのように錯覚させるものが少なくない。しかし、これは事実と異なっており、実際に映画を見れば気付く人もいると思うのだが、DAUの人物たちはカメラの前で即興まがいの演技をしている。モスクワを拠点に活動しているジャーナリストで映画祭ディレクターのボリス・ネレポ(Boris Nelepo)によるとDAUは「『ビッグ・ブラザー』等のリアリティ番組と比較されてきたが、」これらの比較は判断を完全に誤った方向に誘導するものだ。リアリティ番組は「隠しカメラによって撮影される一方で、DAUのチャプターは35mmフィルムだけで撮影されている。…撮影される側はフィルム替えや撮影を行う技師を含む少なくとも三人の同僚たちの前に立つため、自分が演者であることを忘れることなど、ほとんど不可能だ」という。
また、最近ではフルジャノフスキーを含むDAUのスタッフ・キャストたちもDAUの演出方法について、より具体的に語るようになってきた。『DAU. ナターシャ』のほか、DAUの幾つかのチャプターでフルジャノフスキーとともに共同監督としてクレジットされているエカテリーナ・エルテリ(Jekaterina Oertel)によると、彼女はまず「セットを訪れた演者全員に、各々の実際の経歴に沿った内容の職歴を書き与え」たという。「それに応じて、誰との関係が発展し、強化されていくのかが明らかになります。」とフルジャノフスキーはいう。彼によるとその後、演者たちはそれぞれが配属された研究所内の部署で自ずと人間関係を構築していった。また、演者たちは政党に加入するかどうか、政府に協力するかどうか、同僚に関する密告書を書くかどうか等の事柄も自分で判断する。これは「人々のもつ特質、利害、そして願望こそが、彼らのプロジェクト参加、プロット進行、そして新たな現実の創造と破壊への促進力であるべき」というフルジャノフスキーの考えに沿っている。また、撮影期間を通して撮りためたシーンの性質を判断し、どのチャプターに振り分けるかについては、編集作業によって最終的な判断を下していた。DAUのスタッフたちの証言をまとめると、カメラの前における演者の言動、また研究所内での人間関係の展開は、作為と無作為の間で揺れているが、キャラクターごとのプロットはかなりの程度、監督と演者による創作に依拠しているようだ。演者たちは自分が演じるキャラクターのドラマが今後どのような展開を遂げるのかについて、折に触れて監督と相談し合っていたという。研究所での普段の生活や職務の中でドラマとして面白い状況が生じると、演者と監督とで撮影用のプロットを練る、という感じだろうか。監督と演者が共同で制作したプロットと、アマチュア演技によって成り立っている映画であれば、低予算映画の世界ではさほど珍しいものではない。[7][8][1]
沸き起こる非難がDAUにもたらすもの
上記の説明を見ると、DAUは演出と非演出の混交による産物と言える。しかし、これでは世界の多くの人々の関心事であった『DAU. ナターシャ』におけるボトルによる拷問の場面が現実なのか、それともフィクションなのか、単純明快な答えを出すことが難しい。フルジャノフスキーが様々な媒体で語る抽象的で半ば哲学的な作品解説も、既に拷問場面に怒り心頭の人々に対しては、火に油を注ぐばかりである。しかし、DAUがあくまで現代に蘇ったソヴィエト社会を生きた人々の「リアルな」記録である以上、この拷問を完全なフィクションとする訳にもいかない。それはプロとして演技をする役者ではなく、素のままの人間に肉薄しようとするDAUのリアリティーを根本からぶち壊してしまう。エルテリはいかにアマチュア演者が備えている自然さを大切にしていたかについてこう語る。「私たちはただ彼らを50年前の過去の世界に置いただけです。彼らはそれぞれの役を演じましたが、自分自身のパーソナリティーを変えることはありませんでした。彼らは着衣を変え、異なる環境で生活しましたが、それでも彼らの人柄が変わることはありませんでした」。カフェの給仕係ナターシャを演じたナターリヤ・ベレジナヤは、カフェで働いたことこそ無かったが、類似する接客業での経験があった。「それなので、カフェは彼女の良く知る環境なのです」とエルテリは言う。「プロの役者は内的欲求を演じることはできますが、魂の根本要素や実存を再現することはできません」とフルジャノフスキーも彼のリアリズムを強調する。かかる状況につけ込み、映画のPRが実験プロジェクトとしてのDAUのリアリティーを単純かつ声高に強調すれば、性的虐待も現実に行われたのだという印象を与え易い。しかし、世界中のメディアでDAUの悪評が話題になったという状態を一種のパブリシティスタントの成果と見なす向きもあり、それによるとこの状況は必ずしもDAUにとって悪いことばかりとはいえない。DAUに対する人々の怒りは、フルジャノフスキーによるパブリシティ目的のメディア「操作」に起因しているのではないかという邪推である。先にも触れた通り、GQでイドフの書いた監督の醜聞がDAUの広報活動に資したのと同じ原理だ。
歴史を振り返れば、監督アレハンドロ・ホドロフスキーも1970年の自作『エル・トポ』で女優を実際にレイプし、叫び声を上げさせたという自身の主張について、話題作りのためだったと次のように告白している。「あれは事実でなく、単なる言葉にすぎない。無名の存在が映画の世界に参入するためのシュルレアリスト的なパブリシティだよ。」世界が#MeTooを経験した今日、性的スキャンダルはニュースバリューが高い。事実、DAUはその非娯楽的な作品の性質に比して、不釣り合いに大きな予算の回収が課題であるだけでなく、当座の運営資金をさえ必要としていた。DAUのインスタレーション・イベントは「ベルリンで2度のキャンセルに遭い、多くの損失を生みました」とフルジャノフスキー自身が明かしているとおり、いっときDAUは高額の負債を抱え込み、予定していたロンドンでのインスタレーション・イベントを開催する資金さえをも失った。加えて、DAUはその長期に渡る制作期間のため、話題づくりにはひと工夫必要な体質をもつ。約2年強に渡る撮影が終了した2011年の時点では、狭い範囲であったとはいえ、フルジャノフスキーは容易に世間の話題をさらうことができた。しかし、DAUのフッテージがメディアに公開された2015年までには、既に過去の話題性も干上がっていた。そのさらに4年後、パリでのプレミアが行われた2019年の時点でもDAUは再び話題の活性化が必要な状況だった。こうした状況下にあって、DAUを巡る不穏な噂とその秘密主義的な運営姿勢は、安価で有効なマーケティング・ツールとして機能したかもしれない。DAUから解雇された元スタッフが苦情や非難の声を上げてメディアを騒がすこともあったが、いずれのケースでも訴訟には至っていない。かかる状況において、こうしたDAUを取り巻く暗い噂とそれに起因する非難は、あたかもフルジャノフスキーのメディアコントロールの為せる技であるかのように見えたとしても、そこまで不思議ではない。[1][9][8][10][11][12]
ナターシャ役、ナターリヤ・ベレジナヤの怒り
監督のメディア操作の能力についてはさておき、フルジャノフスキーが役者に及ぼす影響力の方はどうだろう。『DAU. ナターシャ』における性的な拷問場面の撮影にあたり、監督はベレジナヤを元スタッフのコワリョーワやジャーナリストのイドフのごとく「コントロール」したのだろうか。第70回ベルリン国際映画祭では『DAU. ナターシャ』を見た多くの映画関係者が監督はベレジナヤを操作したに違いないと感じた。そのためこの会期中はDAUへの非難の声がメディアでの反響を増した期間だった。そんな中、当映画祭における記者会見において、ナターシャ役を演じたナターリア・ベレジナヤは拷問場面への参加が自分の自由な意思に基づいた行為であり、その結果にも満足していると、問題に対する自らの立場を表明している。しかしDAUを非難する映画批評家やジャーナリストたちの間では、映画出演経験の無い、本来ブルーカラー労働者であったベレジナヤが、監督からのプレッシャーや集団心理に押され、やむなく撮影に同意したのではないかという憶測が消えず、彼女がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えている可能性まで懸念された。会見におけるベレジナヤの立場表明も重圧の下における「公式」な見解であって、彼女の本音では無いのではないかと少なからぬ人々が推測した。ここに至り、こうした局外者たちからの非難を過剰だと見なす声も徐々に高まりを見せてくる。「世界各国の映画批評家たちは、ベレジナヤの体験を彼女自身よりも良く理解しているかの如く振る舞い、彼女の主張や自分の体験を定義する彼女自身の権利さえをも無視しているが、これは彼女を見下す行為でもあるのだ」と、女性映画批評家カーメン・グレイ(Carmen Gray)は述べている。
実際、ベレジナヤ自身もこうした人々に対する憤りを隠さない。「ジャーナリストは嫌いなの。知りもしないのに、あれこれ作り上げて」。ベレジナヤは長期の沈黙を破った初めてのインタビューで、こう怒りをあらわにした。フランスの大手メディア、ル・モンドに自分についての記事を掲載されて以来、彼女はインタビューを受けるのを拒否してきたという。この記事の中でル・モンドの記者は、性的な拷問場面に登場した演者(ベレジナヤ)のことを、フルジャノフスキーがBDSM(SMなど嗜虐的性向の総称)専門の売春宿から連れてきた娼婦であったとする誤った情報を掲載した。実際のベレジナヤは不動産業や広告業など様々な仕事に携わりつつ、息子も育て上げてきた母親であり、彼女にとってこれは寝耳に水の事件だった。この一報を受けたベレジナヤは、まずウィキペディアでBDSMについて調べ、その意味に驚くと即座にフルジャノフスキーに電話して事の次第を問い正した。そして、この監督が無実だと確信すると彼女は「イリヤ、私あいつ[記者]の胸ぐらを掴んでやりたいわ」といきり立った。記者の意図を察知していたフルジャノフスキーが「あの記者は君を守りたかっただけだよ」となだめても、彼女は記者を「クズ」だと罵り、怒りは鎮まらなかった。また、ベルリンでの記者会見の際、質問に答える彼女の様子を見ていたジャーナリストたちがPTSDを患っているのではないかと詮索を入れたことについても「彼らが私の何を見てそう思ったのか知らないけど、私は健全な人間よ。そういうおかしな人たちは物事を作り上げているのよ。自分自身のためにね」と怒りに燃える。
フルジャノフスキー曰く「ジャーナリストたちのDAUへの抗議は多くの場合、善意に因むものですが、それにも関わらず彼らは人々の生活を破壊する潜在的可能性も秘めています」とのこと。実のところ、非難に晒された性的な拷問場面は、ボトルを使ってナターシャを尋問するKGB職員を演じたウラジミール・アジッポ(Vladimir Azhippo)と、ベレジナヤ、そしてフルジャノフスキーの三者によって事前に細部まで相談した上で決定した展開だったという。ナターシャは研究所でフランス人科学者と親密な関係を築いていたので、外国人と関係をもつことが禁止されていた当時のソ連にあっては、それが自然な展開だとされた。実生活でウクライナの刑務所職員をしていたアジッポは、当初ベレジナヤの服を引き裂く設定になっていたが、いざカメラを回し始めると彼はこれをためらってしまい、代わりに自分で服を脱ぐよう即興でベレジナヤへ指示した。ベレジナヤは尋問官としての彼の指示に合わせたが、彼女の服を引き裂くのに怯んだアジッポが可笑しく、カメラに背を向けた隙きに思わず笑ってしまったという。因みにDAU.comに掲載されているナターシャの最終経歴についても、ベレジナヤがDAUでの仕事を辞めるにあたって、監督と話し合って決めていた。その際、フルジャノフスキーがナターシャのその後について、どうすれば良いかベレジナヤに尋ねると、彼女は「既に[ナターシャを]逮捕したでしょ。刑務所に入れれば良いじゃない。私をスパイにすればいいのよ」と彼に知恵を授けた。[12][13][7]
ところで、DAUへの非難は性がらみの事柄にとどまらない。セットに到着後、3日目に解雇された通訳の女性によると、DAUのセットの運営状況は酷く乱れたものだった。そのためスタッフたちは常に神経を尖らせており、科学者ダウを演じたテオドール・クルレンツィス(Theodor Currentzis)は「もうセットに来ない」と癇癪を立て、ダウの妻・ノラを演じたラドミラ・ショゴレワ(Radmila Schegoleva)も常に不機嫌だったという。ベレジナヤも先のインタビューの中で賃金の支払いの遅れについて触れている。加えてパリでのインスタレーション・プレミアが不評だったのも、あらが目立つ展示とスケジュールの遅れのせいではないかという意見もある。またロンドンでのインスタレーションのキャンセル、そして欠陥が目立つDAU.comのウェブサイトもDAUの杜撰さを示す例に数えられる。これらを考慮すると、スタッフからの非難や苦情は、DAUのアマチュアめいた運営や人材管理体制が糸を引いているのかもしれない。[14][1][13][9]
以上、長々と書いてきたが、これらはあくまで筆者の目線から見たDAUである。数多くの噂や情報に取り巻かれたDAUだけに、記事に収めきれなかった情報もあり、あるいは筆者の手からこぼれた情報もあるかもしれない。「操作」「コントロール」という発想も、結局真偽の明らかならぬ憶測の域を出ない。ライティングの如何によって、DAUは異なる姿を現す可能性があることにも注意を促したい。
2020年2月27日、第70回ベルリン国際映画祭の会場ではDAUからイリヤ・フルジャノフスキー、エカテリーナ・エルテリ、イリヤ・ペルミャコフ(Ilya Permyakov)の三監督、そして撮影監督のユルゲン・ユルゲスをゲストに迎えたディスカッションが催された。そこで監督らはDAUについて概ねこれまでに書いてきたものに沿った内容を語っており、後日その模様を記録した動画がウェブに掲載されると筆者もこれを目にする機会を得た。動画の後半、ディスカッションに設けられたQ&Aもそろそろ終わるかという頃、司会者の女性は最後の質問者を選ぶため客席に眼を走らせていた。そして彼女に選ばれた女性が話を始めると、これまでの質問者たちのものとは明白に異なるその内容に、筆者の眼は画面に釘付けになった。
「私はDAUを見ていないにも関わらず、ディスカッションを通してこの映画がどういったものなのか、非常にはっきりとわかりました。そのため特に質問はありません。まず、司会者の女性に感謝します。彼女は監督自身の説明以上にこの映画の内容を白日の下に晒したからです。[フルジャノフスキーに向かって]あなたが皆さんの質問をまるでゲームか何かのように言葉巧みにはぐらかしたせいで、私はあなたに都合良く操られてしまったと感じています。DAUのセットにいた人々、クルーや演者の方々がどう感じたかは知りません。もしかすると彼らはこのゲームに参加できて喜んでいるのかもしれない。しかし、私は観客のひとりとして、自分が操作されていることを感じます――それも非常に強く。その気持ちはディスカッションを終えた今でも変わりありません。あと、もう一件つけ加えておきたいのですが、DAUは戦略的に『ビッグブラザー』やそのロシア版の『DOM』シリーズといったリアリティー番組と似ていて、私が思うに、あなたはこれらの手法を真似たにすぎません。おまけに、これによってあなたが達成した唯一のことは、このテレビの手法を映画という媒体に落とし込んだこと、おそらくただそれだけです」。
こう彼女が話し終えると会場の一部から拍手が沸いた。この女性質問者の前には、DAUに参加した女性演者をはじめキャスト一同の心理状態を心配した質問者たちが、各々の懸念をフルジャノフスキーに投げかけていた。この女性質問者の激しい語調は、こうした質問者たちによる文脈を受けてのものだった。しかし、そんな彼女に対しフルジャノフスキーが次のように短く応じると、これもまた場内の一部から笑いと拍手によって迎えられた。「そもそも質問ではないので、答えるべき事柄もありませんが、もしあなたが操作されたと感じたなら、それはあなたの問題であって、私の問題ではありません。」
この女性が決然とした口調で話をしている間、動画には話をする彼女の周囲に着席した参加者の様子も映り込んでいた。そこには「何言ってんだこのバカやれやれ」という表情の男性、「ウヒー!盛り上がってマイリましたっ!」という感じで悪戯っぽい笑みを浮かべて話者を見つめる妙齢の女性、「ネタが取れたぞ、メモメモ」という様子の男性がおり、最後に「…。」ポーカーフェイスの初老の女性が何ひとつ表情を変えぬまま、静かに佇んでいたのだった。[15]
[1]https://cinema-scope.com/cinema-scope-magazine/dau-diary-dialogue-part-one-a-living-world/
[2]https://www.telegraph.co.uk/films/2019/01/24/lights-cameras-madness-troubling-journey-inside-dau-disturbing/
[3]https://112.international/society/scandal-over-dau-film-creators-accused-of-abusing-rights-of-kids-actors-50763.html
[4]https://www.youtube.com/watch?v=r0gvG6rSY7k&ab_channel=PortFilmCo-op
[5]https://www.gq.com/story/movie-set-that-ate-itself-dau-ilya-khrzhanovsky
[6]https://www.npr.org/2014/12/12/370331816/the-never-ending-film
[7]https://www.thedailybeast.com/inside-the-weird-world-of-dau-a-soviet-experiment-that-became-the-most-controversial-film-in-years
[8]https://www.smh.com.au/culture/movies/dau-natasha-is-brutal-intimate-and-the-most-real-film-you-will-see-at-miff-20200818-p55mrl.html
[9]https://londonstudent.coop/khrzhanovsky-my-car-the-story-of-dau/
[10]https://www.artforum.com/news/alejandro-jodorowsky-speaks-out-after-el-museo-del-barrio-calls-off-retrospective-78538
[11]https://www.france24.com/en/20200227-dau-film-shocks-berlin-18-months-after-failed-wall-project
[12]https://www.calvertjournal.com/articles/show/11675/dau-project-natasha-degeration-berlinale-cinema-ethics-krzhanovskiy
[13]https://kinoart.ru/interviews/natasha-berezhnaya-geroinya-dau-my-obgovarivali-kazhdyy-moment-i-s-butylkoy
[14]http://os.colta.ru/cinema/projects/70/details/16912/page1/
[15]https://www.facebook.com/BerlinaleTalents/videos/486718911996434/

林 峻








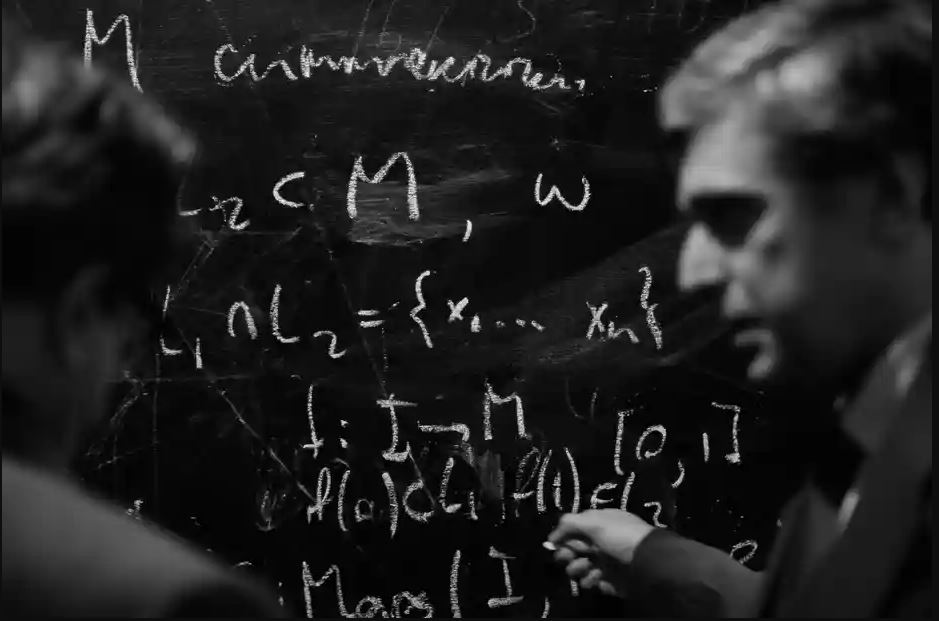







コメントを残す