
今年7月に開催された台北電影節で、蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)監督の最新作『日子』(Days)がクロージング作品として上映された。7月7日の上映当日、会場では記者会見が行われ、蔡監督は自らの最新作を紹介する傍ら、4月に取り沙汰された本作の流出事件について、その後の経過を説明した。台北電影節から既に2ヶ月以上が経過してしまっているが、本件に関しては以前Indie Tokyoでも取り上げたので、その後の展開について、監督の説明を紹介するとともに、彼に関するその他の話題を幾つか取り上げてみたい。
流出騒動のその後
『日子』は、難病を患った男(李康生、リー・カンション)とラオス人青年の生活と交流の様子を映像に収めた作品だ。殆どの場面でカメラは人物たちが1人で行動している時間を撮影しているため、台詞はほとんどない。今年2月のベルリン映画祭に出品され、性的マイノリティを題材にした作品を表彰する「テディ賞」の審査員特別賞を受賞したのち、4月に中国のSNSサイトへ流出した。これを受け、蔡は同じSNSサイトで犯人を非難するとともに流出元の特定を呼びかける檄文を数日に渡って投稿。4年を費やして制作された自作の流出に対し、いつにない動揺を見せている。(この投稿文については、以前こちらに全訳した。)
 蔡によれば、この流出事件の犯人が誰かは既に検討がついており、当面の間はこれ以上この件を追求するつもりは無いとのこと。ちなみに実際に作品が流出した場所は中国ではなく欧米で、映画際へのサンプル(スクリーナー)送付の段階で流出したという。流出させた人物は、蔡が間接的に知っている人物で、誰であるかはほぼ特定しており、相手はまだこちらの動きに気付いていないが、敢てこれ以上の追求は行わない。その理由としては、被害がそれほど深刻ではなかったからだとしている。流出したサンプルの共有は、欧米のごく限定的なグループ内で行われただけであり、それが運悪く中国へと流れ着いてしまった。蔡が流出当時に癇癪を起こしたのは中国での被害が比較的大きかったためだという。だが、そもそも蔡の作品は中国で一切公開されないのが常であるため、この流出による売上への影響は少ないものと思われる。蔡曰く、彼の映画は特定のターゲットをもっており、彼のファンたちは努めて映画館で作品を見ようとする傾向があるという。また「中国では私が撮るような映画を見る人々はごく僅か」だとのこと。この件を報じた台湾メディアも、中国では蔡映画を見ても理解出来ない人が多いため、流出版の共有は徐々に落ち着いていったと、歯に衣着せぬ解釈を紙面に掲載している。
蔡によれば、この流出事件の犯人が誰かは既に検討がついており、当面の間はこれ以上この件を追求するつもりは無いとのこと。ちなみに実際に作品が流出した場所は中国ではなく欧米で、映画際へのサンプル(スクリーナー)送付の段階で流出したという。流出させた人物は、蔡が間接的に知っている人物で、誰であるかはほぼ特定しており、相手はまだこちらの動きに気付いていないが、敢てこれ以上の追求は行わない。その理由としては、被害がそれほど深刻ではなかったからだとしている。流出したサンプルの共有は、欧米のごく限定的なグループ内で行われただけであり、それが運悪く中国へと流れ着いてしまった。蔡が流出当時に癇癪を起こしたのは中国での被害が比較的大きかったためだという。だが、そもそも蔡の作品は中国で一切公開されないのが常であるため、この流出による売上への影響は少ないものと思われる。蔡曰く、彼の映画は特定のターゲットをもっており、彼のファンたちは努めて映画館で作品を見ようとする傾向があるという。また「中国では私が撮るような映画を見る人々はごく僅か」だとのこと。この件を報じた台湾メディアも、中国では蔡映画を見ても理解出来ない人が多いため、流出版の共有は徐々に落ち着いていったと、歯に衣着せぬ解釈を紙面に掲載している。
 『日子』は2013年の『郊遊 ピクニック』に続く、蔡による実に7年越しの長編劇映画である。この長い間隔について記者から問われると、今年で63歳になる蔡は笑みを浮かべつつ、「生きている内にもう一本劇映画を撮れるよう願っています」と応じた。加えて、現在は映画監督として「とても特異な境遇にあるので、通常の映画制作に伴う多くの約束ごとに今後再び順応し直すのは既に不可能」だと断りを入れている。『日子』には事前に用意した脚本が存在せず、カメラを回してはその結果を吟味し、そしてまたカメラを回す、という形で長期に渡って撮影された。この制作方式は、欧米メディアの関心を呼んでいたという。「これは通常のやり方とは違うものの、ひとつの可能な制作方式だと受け止められていました。」蔡は現在の映画業界における制作プロセスについて、「あまりに図式化され過ぎている」と批判している。[1][2]
『日子』は2013年の『郊遊 ピクニック』に続く、蔡による実に7年越しの長編劇映画である。この長い間隔について記者から問われると、今年で63歳になる蔡は笑みを浮かべつつ、「生きている内にもう一本劇映画を撮れるよう願っています」と応じた。加えて、現在は映画監督として「とても特異な境遇にあるので、通常の映画制作に伴う多くの約束ごとに今後再び順応し直すのは既に不可能」だと断りを入れている。『日子』には事前に用意した脚本が存在せず、カメラを回してはその結果を吟味し、そしてまたカメラを回す、という形で長期に渡って撮影された。この制作方式は、欧米メディアの関心を呼んでいたという。「これは通常のやり方とは違うものの、ひとつの可能な制作方式だと受け止められていました。」蔡は現在の映画業界における制作プロセスについて、「あまりに図式化され過ぎている」と批判している。[1][2]
蔡家の「家庭」事情
そんな蔡による『日子』の撮影は、少人数かつ軽装備で手軽に行われ、日記の執筆に近い感覚で撮りたいときに撮影された。それもそのはず、中国語で「日々」を意味する『日子』は、病気を患う李康生の闘病記でもあるからだ。23年前、蔡明亮の映画『河』(1997)の中で、首が回らなくなる奇病を患う主人公を演じた李康生は、本作でも実際に当時から患っている首の病気に悩まされている。『河』の撮影後には手術を行い、一時は状態が改善されたものの、5年前に患った軽度の中風を機に徐々に症状が再発していった。『日子』の撮影中、カメラの前では何事もないように装っていたというが、その闘病生活はかなり過酷なものだったようで、診てもらった50名近くの医師たちも一様に匙を投げ、完治の見込みもはっきりとしない。この状況下で李が闘病のために払った犠牲は、健常者にとって察するに余りあるが、彼には譲れないものもある。「薬の副作用に性機能障害があるって判った時は、すぐに服用をストップしたよ。」この薬は闘病中に併発した鬱病に対し処方されたもので、当時李は2度も命を断つことを考え、遺言まで準備した。「大したことは書いてない。家族や親しい人たちへの財産分与についてだよ。やっぱり苦労して稼いだお金だし、良い相手に受け取って貰いたくて。」そんな李が闘病生活で最も感謝している相手は自宅で同居する蔡監督と、現在李が交際しているガールフレンドだ。人生に区切りをつけるという李の考えを告げられた二人は仰天して必死に看病した。ガールフレンドは台北郊外の山中にある廃墟を改装した李と蔡の家まで度々足を伸ばしてくれた。彼女との関係は良好のようで、今年で52歳になる李だが、今は家庭を持つことを望んでいるという。「日頃、やることもなく家に居ると、子供がいて賑やかなのも良いなと感じるんだ。子供がいれば遺産も残せるし。」
▼絵を描くツァイ。左壁面の絵は友人のCMディレクターにより10万NTD(36万円)で買い取られたという。蔡「こんな楽に稼ぐ方法があったんだ(笑)」 李と共に暮らす蔡はというと、医者から菜食を勧められた李のために食事を作り、毎日知恵を絞って献立を考えたり、わざわざ街まで食材を買いに出掛ける事もある。用事で外出する時には、家を出る前に食事を用意し、冷蔵庫にメモを貼っておく。「冷蔵庫に豚肉と鶏肉のフライがそれぞれ2皿づつ用意してあるから、そのままオーブンで30分加熱して。あと、各種月餅(胡椒×2個、玉ねぎ×10個、蓮の葉×1個、大根×1個)は焼いて食べること。蒸し鶏はそのまま食べて。」一見、蔡の温かい老婆心を感じるメモだが、李によれば「ほっとけば自分で外に行って適当に食べるのに、「これを先に片付けろ」っていう意味なんだ。」とのこと。このメモは李が自宅を訪れたテレビ番組の取材班に公開したものだが、本来は冷蔵庫に貼ってあったものを、取材が来ると知った李が「みっともないから」と、しまい込んでいたものだった。共に暮らす家族のような存在だという李との関係に話が及ぶと、蔡は説明が難しいとしつつこう解説する。「私か李が女性であればお互い結婚することができますが、私たちは違います。私たちは友人で、これはとても素晴らしい関係なのです。」[3][4][5]
李と共に暮らす蔡はというと、医者から菜食を勧められた李のために食事を作り、毎日知恵を絞って献立を考えたり、わざわざ街まで食材を買いに出掛ける事もある。用事で外出する時には、家を出る前に食事を用意し、冷蔵庫にメモを貼っておく。「冷蔵庫に豚肉と鶏肉のフライがそれぞれ2皿づつ用意してあるから、そのままオーブンで30分加熱して。あと、各種月餅(胡椒×2個、玉ねぎ×10個、蓮の葉×1個、大根×1個)は焼いて食べること。蒸し鶏はそのまま食べて。」一見、蔡の温かい老婆心を感じるメモだが、李によれば「ほっとけば自分で外に行って適当に食べるのに、「これを先に片付けろ」っていう意味なんだ。」とのこと。このメモは李が自宅を訪れたテレビ番組の取材班に公開したものだが、本来は冷蔵庫に貼ってあったものを、取材が来ると知った李が「みっともないから」と、しまい込んでいたものだった。共に暮らす家族のような存在だという李との関係に話が及ぶと、蔡は説明が難しいとしつつこう解説する。「私か李が女性であればお互い結婚することができますが、私たちは違います。私たちは友人で、これはとても素晴らしい関係なのです。」[3][4][5]
▼冷蔵庫のメモを読み上げる番組司会者。2人が食したカレーは蔡のお手製
蔡明亮の廃墟観
実は蔡自身も李の難病が発症する以前に、体調を崩しパニック障害にかかっていたことがあった。その際、療養のため静かな山の別荘を探していた蔡は、山をドライブ中に建設途中で放置された建物に目を止めた。下車して中を確認し、この廃墟を気に入った彼は購入を決定。建設業者を探したが、しかし建物を放置した責任者は既に行方をくらませた後だった。諦め切れない蔡は「一日だけでも良いので、この廃墟に住めますように」と、ひたすら仏に祈ったところ、ある日、李がネットで売りに出されていたこの廃墟を発見。晴れて購入となり現在に至る。実際に住んでみると、建物から外を眺めた際の素晴らしい景観に、蔡は新居への帰属感を強めたという。今では近所を走るバスの運転手とも顔見知りになるほど、蔡はこの場所に溶け込んでいる。「山奥の廃墟での生活は、世界に対する私の認識を一新させました。私は今まで様々な場所に行ってきましたが、どこも常によそよそしく感じられ、帰属意識を感じたことはありませんでした。しかし、この廃墟に出会った現在では毎日の外出が嫌になるほどで、日々異なる様子を見せる野山の景色をゆっくりと眺めていると、時の移ろいを目撃しているような気持ちになります。」この時の移ろい、そして時の動きの痕跡が克明に刻まれているのが廃墟なのだと彼は言う。「廃墟は徐々に朽ちてゆき、最期には倒壊します。そんな古い家や廃墟は、どこか饒舌な老人と似ていて、あなたに生についての多くの事柄を語るのです。廃墟は天が時間を用いて作り上げた作品なのです。」[5][6][7]
ここで蔡の廃墟についてのこのコメントを少し考えてみたい。蔡は廃墟や老人の面持ちのうえに、時の刻印を発見する。建物や人の体にゆっくりと浸透して老化を進め、やがて終末へと導く時間の作用を、廃墟や死に近づく老人の形相の上に見て取る蔡の眼差しは、「歴史は髑髏の相貌のなかにその姿を現す」とする思想家ヴァルター・ベンヤミンの廃墟観を思わせるものがある。ベンヤミンにとって「歴史はとどまるところを知らぬ凋落の経過として現れる。」そしてこの「凋落の経過」が死にゆくものの相貌として具現化したものが崩れ行く廃墟であった。死にゆくものの中には過去の記憶が秘められている。ベンヤミンは、廃墟をかつてそこに存在していた人間の気配に満たされた「場所」、つまり死せる時間としての記憶を閉じ込めた「器」として解釈した。ツァイは言う。「廃墟には、夢や記憶といった目に見えない何かが存在するように想えます。」長いこれまでの生の記憶を内に秘めた老人の顔のように、廃墟はその内部にある今は亡き死せる過去を物語るである。例えばハーク・ハーヴェイのホラー映画『恐怖の足跡』(1962)やマルグリット・デュラスの『ヴェネチア時代の彼女の名前』(1976)に登場する廃墟、そしてアンドレイ・タルコフスキーの『鏡』(1975)における朽ちた部屋々は、ベンヤミンの死せる過去の「器」としての廃墟という発想と、大枠において呼応する例として挙げられるが、蔡の作品はどうだろうか。廃墟は「自分の「声」を持っていて、夜ライトを消して寝ていると聞こえてくる事がある」と廃墟での不思議な体験について語る蔡は、これまでの自作の中で頻繁に廃墟を超自然的な舞台として描いてきた。彼の廃墟はしばしば劇中で生死の区別がつかない存在、あるいは死者の住まう場としての役割を担っている。その最たる例のひとつは、2017年における蔡による初のVR作品『家在蘭若寺』(邦題:蘭若寺の住人)におけるシャオカンが住む廃墟だ。蘭若寺(らんじゃくじ)とは中国清代の怪異短編小説集『聊斎志異』(りょうさいしい)の一編に登場する幽霊寺のことだが、今日の中国語では意味が一般化していて単に「霊の出る場所」の総称である。そこで『家在蘭若寺』という作品タイトルを日本語に訳すと「我が家は蘭若寺」となるが、実に本作のロケは蔡たちの「我が家」である廃墟で行われている。撮影開始前にはこの廃墟の未改装の箇所で自殺者の遺体が発見されたため、監督の発案により自殺した女性というチェン・シャンチーの役柄が急遽決定した。本作でも体を病んだ主人公シャオカンは、廃墟で寝起きし、既にこの世を去った母の亡霊と共に暮らし、彼女に看病されており、隣室にはチェン・シャンチー演じる女性の幽霊が暮らしている。蔡は言う。「あらゆる幽霊は廃墟の中に囚われているんです。劇中の幽霊も廃墟に閉じ込められ、不当に抑圧され、不満をもっているため、廃墟に入ると彼らが嘆いたり溜息をつくのが聞こえてきます」[8][9][10][11][16]
『Hole-洞』のロケ地が現在は有名心霊スポットになっていることについて
蔡の幽霊物件に対する鑑識眼は、台湾社会からも太鼓判を押されている。というのも過去の蔡映画のロケ地が、後に台湾で最も有名な心霊スポットのひとつに成長して現地のオカルトファンたちを惹きつけているためだ。蔡が1998年に撮った初のミュージカル『Hole-洞』は、粗末な造りの古びたマンションの床に穴が空き、上下階の部屋が通じてしまうという惨事を不思議タッチで描いたミュージカル・コメディ。そもそも穴の空いた不気味な公団住宅で人々が歌って踊るのを見て楽しむことが趣旨なので、映画の最優先事項は恐怖を煽ることではないのだが、雨に濡れた薄暗い公団住宅の廊下や、照明の切れたエレベーターホールなどは否が応にも不気味に映る。映画のロケに使われたのは台北市が管理する公営住宅〈西寧マンション〉(中国語では西寧國宅)。台北駅の最寄り出口から徒歩10分、台北有数の繁華街である西門町にも近く、すぐ隣にはスポーツセンターまであり素晴らしい立地条件を備えている。しかし、1982年築の建物の内部は薄暗く、整備も行き届いておらず、外観は都市の汚れた外気と亜熱帯気候の降雨量に晒されて薄汚れている。一種のミニチュア版九龍城砦と呼ぶに相応しい、そこそこに大きなこの建物の一階には、中規模のスーパーに加え、電子機器店をはじめとした個人商店、ついでに交番まであり、それなりに便利ではあるが、空間全体がうらびれていて憂鬱な雰囲気が漂う。Holeの撮影から既に22年が過ぎ去った現在、建物の老朽化は当時以上に著しく、台北の有名心霊スポットとしての貫禄は十分だ。
この西寧マンションについて、ネット上では「部屋でキーボードを叩く音が聞こえる」などといった、奇怪な噂が数多く出回っている。なかでも最も有名な話は、屋上から飛び降り自殺を試みた少女についてのものだ。自殺を思いとどまるようその場で説得を試みた警察に少女が話した説明によると、彼女が西門町の靴屋でボーイフレンドと靴の試着をしていたところ、突然頭が朦朧となり抗し難い力に導かれて西寧マンションの屋上へとたどり着き、下を見ると大勢の人々が手招きしていたという話だ。この手の話はマンション1階に入居している交番内にも存在し、夜勤中に仮眠を取っていた警官がベッドの上で目覚めると、体の位置が180度回転しており、足には手の跡が青く残っていたらしい。その後、仮眠室は取調室へと変えられたという。こうした噂は単に老朽化した建物の不気味さから人々が想像した産物ではない。実際、このマンションは建物全体で多数の死者が出ている事故物件であり、これまでには飛び降り、転落、エレベーター事故、練炭自殺、殺人と多様な事故・事件が起きている。去年だけでも16階から人が落下する事件が2件、2004年には実に9件の事故が発生した。数ある事件の中には、どのように入り込んだのか、70歳の老女がエレベーターシャフトの中で全裸で死んでいたという、現在まで未解決の怪事件もある。当然これらの事件を超自然的な力によるものと考える事もできるが、理屈によって解釈するための材料もまた幾つか存在する。1)元来この公営住宅は台北市が低所得者支援のために建設した低家賃(3,700~8,300NTD、約13,000~30,000円)のマンションで、入居条件のひとつに年収額の上限を設定しており、貧困高齢者たちが集まっていること。2)近場に他の高層住宅が存在しないこと。3)自殺の名所として知名度を上げてしまったこと。4)巨大な建物内部の人口が過密状態であるうえに、居住スペースとオフィススペースへの雑多な出入りのために管理が行き届かないこと等。これらの条件がマンションでの事件数に影響しているのではないかと見る向きもある。
▼2019年に転落した39歳の女性。16階から11階の落下防止用ネットまで転落した ▼潜入映像(中国語)
▼潜入映像(中国語)
実は『Hole』の撮影時にも、クランクインから三日が経過した時点で飛び降り自殺が1件起きており、皆おびえていたと当時のスタッフは証言している。蔡自身は幽霊をそこまで恐れいる訳でも無さそうだが、かといって上に幾つか上げた例のような「合理的」解釈を行っている訳でもない。昨年のヴェネチア国際映画祭で4Kリマスター版が公開された『楽日』(2003)でも、幽霊が出るという噂のある劇場を描いている蔡は、幽霊建築に対しても詩的な色合いの強い独自の見解を持っている。蔡によれば、彼が『家在蘭若寺』で描いた幽霊建築は、死者と生者が交わる場所、「死と生の境界」なのだという。「生きている人間がひとたびこの境界にたどり着いた時、私たち生者はどのくらいの時間この境界に留まることができるでしょうか?『家在蘭若寺』が語るのは(時間の中で)流動する生命の移り変わりなのです。この世界には我々に見えないものも存在します。目には見えずとも向き合うことが必要な存在もあるのです。(死者である母と生者であるシャオカンとの交流、つまり)記憶と現在との交流は、現実の中で起きるのでしょうか、それとも夢の中なのでしょうか?」
ある日、最寄りの低所得者支援住宅を訪れ、この問いについて深く内省するのも悪くないかもしれない。[11][12][13][14][15]
▼『Hole-洞』
[1]https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=91071
[2]https://6do.news/article/2911961-61
[3]https://today.line.me/tw/v2/article/Jqxwx3?utm_source=copyshare
[4]https://star.setn.com/News/766237
[5]https://youtu.be/OXUsaaLzw_U
[6]https://star.setn.com/news/781822
[7]https://youtu.be/gmistpcaeko
[8]https://www.mirrormedia.mg/story/20170829ent016/
[9]https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyoiku1932/59/2/59_2_172/_pdf
[10]W・ベンヤミン(浅井健二郎訳)『ドイツ悲劇の根源 下』51頁(筑摩書房, 1999)
[11]https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1121026
[12]https://udn.com/news/story/7320/4083587
[13]https://www.storm.mg/lifestyle/1513520?page=1
[14]https://youtu.be/ZWNE2CPAiS8
[15]https://news.ebc.net.tw/news/fun/150327
[16]https://www.hypesphere.com/news/14957

林 峻
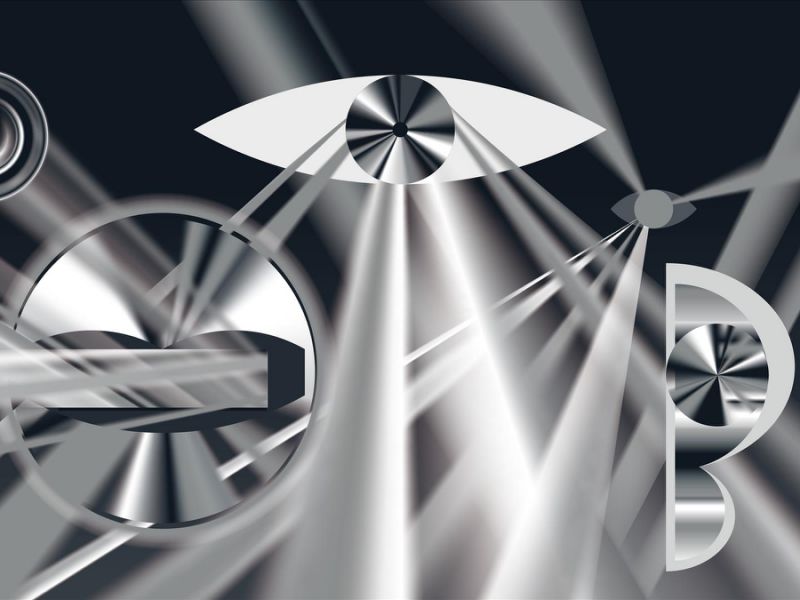












コメントを残す