基本のストーリーは至ってシンプルだ。ある家族をめぐり、一つの事件が起きる。鍵となるのは、その家族と親しく付き合っていた、妻の親友である。ではなぜ、その事件は起きたのか、映画を観ていく中で、私たち観客はその経緯を知ることになる訳で、普通の作品であれば、事件に至るまでの彼らの心の動きと、彼ら、特に妻とその親友の関係に焦点が当てられ、そこが物語の主軸となっていくのではないかと思う。しかし、この作品は少し異なる。物語は分解され、各シーンの撮影風景、登場人物を演じる俳優達が、時にはセットですらない殺風景な室内で、椅子に腰かけて台本を読む光景が目の前に展開される。さらには、通常、公開される完成された映画では見られることのない、同じシーンのリテイクが時に何度も繰り返される。本筋となる物語の時間軸すらあいまいなまま、「映画の登場人物」ではなく、「登場人物を演じる俳優」が、台本(実際に手に持っている)を読んでいるシーンが続くのだ。映画に限らず、演劇などもそうだと思うが、制作現場に携わっている人間であれば、当たり前に目にしているはずのこれらの光景。私のように見る側、受け手側にいる人間にとっては、それを映画の中で続けて見せられること自体、新鮮な経験であるとともに、さらにはそこからまた別の物語、つまりは俳優が登場人物に変わり、関係が生まれていく瞬間を見ることができ、その別の物語によって、本筋への理解が深まる、という不思議な映画体験をすることにもなる。そういったシーンの連続は、最初は退屈にも思えるのだが、明らかに空気が変わる瞬間が見えてくる。それまで与えられた台詞を読んでいた俳優たちが、それぞれの過去と事情を抱えた登場人物に変わり、それぞれの個性を持った登場人物が集まって会話することで、人物間の関係性が明確になり、そこで初めて「王国」の持つ意味が浮かび上がってくるのだ。
草野なつか監督によると、タイトルの「王国」は、奈良原一高の同名の写真集から取ったものだという。男子修道院と女子刑務所という、全く異質のようでありながらも、外界と隔絶され、さまざまな制約がある中での静かな生活、という意味では同質であるともいえる二つの場所で撮影された有名な写真集であるが、私自身、静謐さに満ちたこの写真集に魅了され、一時間に一本の列車に乗って、舞台の一つであるトラピスト修道院に行ったことがある。実際にたどり着いたその「王国」は、不安になるほど人気のない豊かな自然の中を一本通る、きれいに舗装された長い長い道を歩いて、さらにその先に続く長い階段を上りきったところにあり、修道院名が書いてある鉄の門扉で外界から隔てられた、簡素な佇まいの場所だった。中に入ることが許されていないことは承知の上だったが、門扉、そして、修道院の周りを覆う柵の間からでは、建物すらよく見えず、辺りの散策だけして帰ったのだが、都内では決して経験できないような静けさの中で「こういう中で外界の喧騒と離れて暮らせたら幸せかもしれない」という思いがよぎったのを覚えている。
この作品の中で描かれる「王国」は誰の中にも存在しうるものである。それはシーツと椅子、合言葉といった簡単なもので作ることができるものであり、時にはそんなものすら必要としない。「王国」を規定するのは、自分と誰かとの関係性であり、自分と誰かとの間のルールであり、そういった目に見えないものが、修道院を囲む柵のように「私たち」を囲み、「外の世界」から引き離し、守ってくれるものになる。しかし、その関係とルールによって守られた「王国」の中で暮らすことは、保証された幸せなのだろうか。また、ある「王国」に属することが、別の「王国」に残ることの妨げになるかもしれない。
最初から完成された演技を見せられるのではなく、登場人物になっていく、その過程が描かれることで、より一層、「王国」の意味するものが可視化される。制作過程を晒すことが、決して楽屋落ちにならず、主題を際立たせることにつながっている、非常に稀有な作品であると思う。
『王国(あるいはその家について)』は、2月8日(金)より開催される第11回恵比寿映像祭にて上映されます。
恵比寿映像祭公式サイト
また、関西地区では2月9日(土)より出町座、元町映画館、シネ・ヌーヴォの3館で開催される特集「次世代映画ショーケース」にて上映されます。
「次世代映画ショーケース」公式サイト
『王国(あるいはその家について)』
(2017-2018年/カラー/スタンダード/150分)
監督:草野なつか
出演:澁谷麻美、笠島智、足立智充、龍健太
脚本:高橋知由
撮影:渡邉寿岳
音響:黄永昌
編集:鈴尾啓太、草野なつか
エグゼクティブ・プロデューサー:越後谷卓司
企画:愛知芸術文化センター
制作:愛知県立美術館
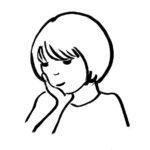
佐藤更紗
国際基督教大学卒。映像業界を経て、現在はIT業界勤務。目下の目標は、「映画を観に外へ出る」。
